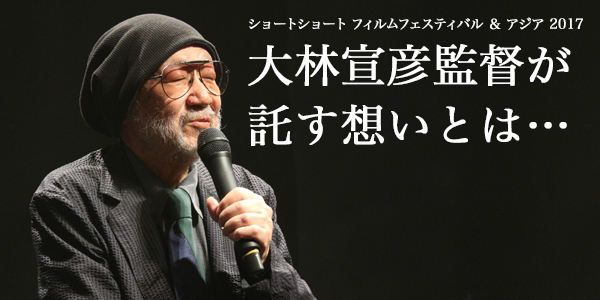|
|
今年の「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア」アワードセレモニーは、いつにない緊張感に包まれた。既にあちこちのメディアで報道されてきた審査委員長の大林宣彦監督の30分に渡るスピーチ。戦後初めて憲法の改正に揺れる現在の日本において、これからの日本人クリエイターは、何を表現し、何を語るべきなのか…会場にいた若手クリエイターたちに大林監督の言葉はどのように届いたであろう。 始まりは昨年8月。大林宣彦監督の76年に渡る映画人生の集大成として、架空の街で平和を願う戦前の若者たちの日々を描いた檀一雄の原作『花筐(はなかたみ)』の撮影に入ろうとした前日、肺がん第四ステージ、余命三ヵ月という宣告を受けた…という独白に会場は凍り付く。本来、長編映画デビュー作には、この『花筐(はなかたみ)』を…と考えていたところ、檀一雄の死去によって話が立ち消えになったという曰く付きの作品。もしこの映画化が実現していれば、あの伝説の名作『HOUSE』は生まれなかったのだから皮肉な話しだ。「本当はもうここにいないんですが…まだ生きております」場の雰囲気を和ませようとしたその言葉に、会場にピンと張りつめていた緊張感が一瞬和らぐ。「そんなわけで生きているなら…」と、かつて親交の深かった黒澤明監督が大林監督に残した(託したと言った方が正しいか)言葉を引用して、今の日本が置かれている状況と、今を生きるクリエイターたちは表現者として何をすべきなのかを語ってくれた。その時間…30分。用意された椅子を断り、ステージの中央に立ったまま、ゆっくりと口を開いた。東宝の専属から離れて独立プロダクションを設立し、会社制度から離れて自由な表現者となった黒澤監督。ようやくアマチュアになれた事への喜び。「アマチュアというのは良いねぇ。俺たちが提げた戦争という制度にも縛られて、何にも表現の自由が無かったけれども、今やアマチュアとして自由に僕の表現したい事をやるんだ」という黒澤監督の言葉を紹介する。
黒澤監督が、黒澤プロダクションを設立したのは1959年(昭和34)。日本を取り巻く様々な問題を時代劇や犯罪映画などのカタチを借りて切り開いていた偉大なるアマチュアだった。「映画には、必ず世界を戦争から救う、必ず世界を平和に導く、美しさと力がある」と信じていた当時80歳の黒澤監督は大林監督に次の事を託した。「戦争はすぐに始められるけど、平和を確立するには少なくとも400年は掛かる。俺が400年生きて映画を作り続ければ、俺の映画できっと世界を平和にしてみせるけど、俺の人生はもう足りない。大林君はいくつだ?そうか50歳か…俺が80年掛かって学んだことを君は60年でやれるだろう。そうすると君は20年俺より先にいけるぞ。君が無理だったら君の子供、さらにそれがだめなら君の孫たちが、少しずつでも俺の先をやって、そしていつか俺の400年先の映画を作ってくれたら、その時にはきっと映画の力で世界から戦争がなくなる。それが映画の力だ」 1910年(明治43)生まれの黒澤監督に対して、1938年(昭和13)生まれの大林監督。自らを「ジジィでございます」と紹介する。ジジィと言われる世代は、つまり、戦争を知っている…戦争を体験した世代という事だ。「私の二つ三つ兄貴の世代が、しっかりそこを頑張って、いろいろ伝えて表現してくれていたんですけれども、この2〜3年で皆あの世に逝ってしまい…思えば私がその世代を知っている最後の弟分になりました」そして、大林監督の続けた言葉に、既に分かっていながらも、改めて衝撃を受ける。「戦争の時代っていうと、何か時代劇観ているような、遥か昔の話しと思うかも知れませんが、戦争というのはね、ここにあったんですよ」 ここにあったんです。 …と、手に持っていた杖でステージをドンドンと鳴らす。ここ東京に…ここ日本に…。 「この日常の中に戦争はあったんです」少年だった大林監督は、日本が真珠湾奇襲攻撃に成功したニュースに、「日本が勝った!敵負けた!ルーズベルトやチャーチルをやっつけた!日本の正義は大したもんだ!」と、提灯担いで皆で浮かれていたという。尾道の医者の家に生まれた大林少年は、二階の大広間で大人たちが集まり天下国家を論じる光景を見てきた。しかし、わずか4年で情勢はどんどん変わり、誰の目にも戦局の悪化が色濃くなっていた頃、衝撃的な場面を目の当たりにする。肺を病んで戦争へ行けなかった叔父が漏らした本音…もう日本は負けるよ、負けた方が良いよ…その翌日、姿を消した叔父が数日後に青あざだらけで帰って来た時、連れて来た顔見知りの(いつもは大人しい)憲兵の形相に「人間の顔ってこんなに権力によって違うのか」と大林少年は思ったそうだ。やがて敗戦へと向かう日本…大林監督の奥様でプロデューサーの大林恭子さんは、3月10日の東京大空襲を死ぬ思いで逃げ延びた。遠くの夜空に見える焼夷弾を指差して恭子さんの父は「花火のように綺麗だろう?しかし、この花火ひとつひとつの下で今、人が首をもがれ手足をもがれ命を奪われているんだぞ!よく見ておけ!人間というものはこんなに愚かしい生き物だぞ!」と言ったそうだ。 そして…大林監督が住む広島に原爆が落とされて間もなく、戦争は終結した。 戦争にも理屈がある…戦争をすれば経済が高まるという事も間違いない事実だ。色々な理屈があって戦争が再び起きる事は充分あると指摘した大林監督はこう続けた。「より強い国の核の下に入れば守ってくれると言って、守ってくれた事がありますか?今後も決してありません。自国は自国のためだけに戦争します。あるいは抑止力なんてありますか?抑止力なんてあった試しがありません。そういう戦争の理不尽を良く知っていた私たちがいなくなってしまった事…この断絶が怖いです」悲しいかな…何が何でも戦争なんて嫌だ!金が儲かろうと嫌だ!と言い切れる第一次・第二次世界大戦の虚しさや恐ろしさを生身で知っている人間がどんどんいなくなっている現実。戦争の実態を知っている政治家がいなくなった時、人間として責任を用いれない物になって行くのでは…という怯えがあるという。
さて、大林監督が、会場の映画人に向けて述べられた言葉の意味を理解するためには、大林恭子プロデューサーが公言するふたつの自主映画『この空の花 盛岡花火物語』(平成24年)と『野のなななのか』(平成27年)を語らなければ話しにならない。 『この空の花 盛岡花火物語』は、放浪の画家・山下清の作品“長岡の花火”で有名な、新潟県長岡市で毎年8月に開催される長岡花火大会をモチーフに長岡の歴史と、語り尽くされていない戦時中の事実を描いている。太平洋戦争末期の長岡空襲で亡くなった犠牲者を追悼する意味で開催されている花火大会を初めて見た大林監督は涙し、山下清の遺した「みんなが爆弾なんかつくらないできれいな花火ばかりをつくっていたら、きっと戦争なんか起きなかったんだな」という言葉に感銘を受けて、映画製作の決心を固めたという。この映画で初めて盛岡が原爆投下の候補に挙がっていた事を知り、更には広島の一ヵ月前に模擬原子爆弾(パンプキン爆弾)を投下して実験を行っていたという事実に怒りを覚える。クランクインの直前。新潟県を襲った豪雨で花火大会の会場が水没。映画の撮影はおろか大会開催も危ぶまれたが、長岡市長は「イベントの花火大会なら中止は当たり前だが、長岡花火は祈りのメッセージ、これを世界に発信しなければ」と決行の決断を下し、官民総出で会場の汚泥を除去して開催にこぎ着けたという。映画が完成した年の3月には、ホノルル市と長岡市は姉妹都市締結式が行われ、大林監督もハワイに渡り、『この空の花 盛岡花火物語』を上映。ワイキキ沖で平和への祈りが込められた約1500発の花火が打ち上げられた。―安倍首相がオバマ大統領と共に日本の首相で初めて真珠湾へ公式に訪れた4年前の事だ。 話しは変わるが『この空の花 盛岡花火物語』の製作が発表された直後に起きた東日本大震災によって製作自体が危ぶまれたが、自粛ムードが日本全体を覆う中、こういう時だからこそ…と、脚本を改訂して製作を続行する中越地震の爪痕が残る長岡市内の旅館で台本を完成させる。物語も震災をふまえたものに修正され、中越地震の被災者にも触れている。そして、完成後には、大林監督自らが福島県の南相馬市や飯館村を訪れていたのだが…それらを全て破壊する事件が最近、新潟市の小学校で発生してニュースで取り上げられた。福島第一原発の事故で新潟市に避難していた小学4年の男子生徒に、担任の教師が生徒と共に「菌」呼ばわりしていたあの事件だ。中越沖地震で柏崎刈羽原子力発電所が被災して、共通の痛みと恐怖を味わった県民とは思えない行為に、人間の心に対するやるせない不信感を抱いた人も多かったのではないだろうか?『野のなななのか』に出て来る南相馬市の女性が言う「今は普通でいられる事がありがたいです」というセリフが心を突き刺す。
こうした現実を受けて、大林監督が疑問を投げかけた『正義についての定義』の下りが、深く印象に残る。「私たちは正義を信じていますよね?一体、正義って何でしょう?」戦時中は鬼畜米英とアメリカ・イギリスが悪で、日本(勿論、同盟国のナチスドイツも)が善と教えられていた子供たち。「私たち戦争中の子供は、しっかりそれを味わいました」という大林監督のひと言が重く伸し掛かる。「私たちも大日本帝国の正義のために米英と戦って潔く死のうと覚悟した少年でした。しかし負けてみると鬼畜米英と言われた米英の正義が正しくて、日本の正義が間違っていた。なんだ…正義とは結局、勝った国の正義が正しいのか…それが戦争とうものか。じゃあ自分の正義を守るためには年中戦争してなくてはならないじゃないか?」しかし、大林監督は、その敗戦の中から生まれた日本国憲法…とりわけ、憲法九条について「奇跡のような宝物を手に入れました」と述べている。「世界中の国家が全部、憲法九条を持っていたら世界から戦争は無くなるんですよ」 そして、ソ連軍の樺太侵攻や北海道の炭坑で働かされた朝鮮人の遺骨収集など…あまり語られていなかった太平洋戦争のもうひとつの側面を描いた『野のなななのか』。公開時にキネマ旬報5月下旬号において、作家・中川右介氏との対談で「各論」と「総論」の違いについて話されたいたのを思い出す。高度経済成長期の頃から日本人は「各論」でものごとを考え始めた。「各論」とはトータルではなくジャンル分けする事だ。そう、派閥という言葉も政治の世界で聞かれるようになったのもこの時代だ。大林監督は「高度経済成長期からバブルに至る情報時代が日本をおかしくした」という。ものごとの本質を深く知るには全体の流れを見る「総論」も必要なのだ。例えば原発。これを経済という「各論」だけで考えると必要なものかも知れないが、もっと未来のことまで引いた「総論」で考えると、おかしいのでは?となる。これは、集団的自衛権や秘密保護法などについても同じ事が言える。「各論」で考えると国を守る…という大義名分が成り立つとしても「総論」で考えた場合、陰に潜む危険性がよく見えて来る。 「各論」は情報。 「総論」は物語。 このふたつを読み取るのには「想像力」が必要。 ところが、ここ数年の日本の政治には「想像力」が足りないのでは…と思う。「各論」だけの議論が多い。大林監督が抱き続けている疑問…というかジレンマは、ここから来ているのではないだろうか?その「想像力」を奮い起こさせるために映画が出来る事とは何だろうか?「戦争という犯罪に立ち向かうには、戦争という凶器に立ち向かうには、正義なんかでは追いつきません。人間の正気です。正しい気持ち。人間が本来自由に平和で健やかで、愛するものと共に自分の人生を歩みたいという事がちゃんと守れるのが正気の世界です。政治や経済や宗教までもが、正義を謳う時、私たち芸術家(表現者)は、人間の正気を求めて、正しい人と人の幸せの在り方を築いていこうじゃありませんか」映画は「記録装置」ではなく「記憶装置」…この言葉は、大林監督に黒澤監督が残した言葉だ。「この混迷の時代ですけれども、どうか皆さんも映画の力を信じてください。未来に向けていつか黒澤明の400年目の映画を私たちが作るんだと…」
今、世界は混乱している。怒りを怒りによって封じ込めるから新しい怒りが誕生する。そして、その矛先は全く関係のない子供たちや一般の人たちに向けられている。それまで遠い国の話しと思っていた日本も隣国の情勢によって、そろそろ真剣に向き合わなくてはならないところまで来ている。原爆を落とされた広島県に育った大林監督が何度も何度も繰り返す「そのことを私たちが、今忘れてしまっている。この忘れてしまっていることが、今の時代の大変な悲劇になっている」という言葉を今一度自分の頭で噛み締め、想像力を豊かにして、考えるべき時が来ているのではないだろうか。 「ジャーナリズムとは、庶民1人1人が語るものであり、民主主義の多数決なんかではない。少数者の意見が尊ばれることこそが、健全な正気の社会なのだ」という大林監督の言葉は果たして、会場にいた若きクリエイターの胸にはどのように響いたであろうか?今年の作品は例年よりも素晴らしいものが多かったものの、大林監督が総評として繰り返し言っていたように、作品の中にはヒリヒリとした危機感を感じさせるものは無かった。現在のこの日本において…それで良いのか?と思う。「映画とは風化せぬジャーナリズムである」そう断言する大林監督の言葉に長年映画の世界に生きて来た映画人だけが言えるある種の覚悟が見える。そして、全世界の映画人たちに向けて締めくくられた言葉…若きクリエイターたちよ、ここで応えられなければ嘘だ。そして願わくば、大林監督のメッセージを「挑戦」と受け止めて、奮起する気骨のあるクリエイターが現れて欲しい。 「若いひとたち…俺の続きをやってよね」 取材:平成29年6月11日(日)明治神宮会館「アワードセレモニー」にて |
|
|
Produced by funano mameo , Illusted by yamaguchi ai
copylight:(c)2006nihoneiga-gekijou |