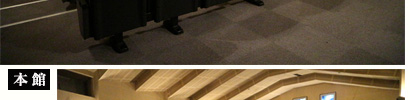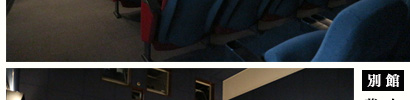|
三重県伊勢市駅は、伊勢神宮外宮の最寄り駅であることから、季節を問わず多くの参拝客で賑わっている。まずは外宮を参拝して、それから本殿となる内宮を参拝する…これが伊勢神宮の正式な参拝方法だ。だから殆どの乗客は、まず駅から真っすぐ延びる参道を外宮に向かって歩いて行く。だから午後も14時を回ると人の流れも落ち着きをみせ始める。そんな人の流れに逆らって線路沿いを宮町方面に向かってボチボチと歩く。道沿いにJRの車庫線があるから鉄道特有の油と鉄の臭いがする。しばらくすると、しんみちというアーケード街の入口が現れる。長いアーケードの出口が見えて来るとスナックや小料理屋が多くなってくる。昔はこの辺りに遊郭があって、駅から離れたこの場所に飲み屋が多いのもその頃の名残りだ。そんなアーケードを抜けたところに、芝居小屋から始まった映画館『進富座』がある。「今日は珍しく、朝からたくさんお客さんが来ているんだよ」劇場前の広い駐車場に停まっている車を見て嬉しそうに話してくれたのは、4代目館主・水野昌光氏だ。開場を目指して朝早くから駐車場に入って来る車を誘導するところから昌光氏の一日が始まる。 古市にあった江戸時代初期から続く、十返舎一九の東海道中膝栗毛にも登場する芝居小屋“長盛座”の支配人だった昌光氏の曾祖父・寺田庄太郎氏が、現在の場所に芝居小屋を借りて『新富座(当時は、進ではなく新だった)』という館名で始めたのが昭和2年3月のこと。当時、人気を博していた東西の役者を招き、芝居興行を営んでいた。「僕の祖母は二代目の中村鴈治郎さんと仲が良かったそうですよ。また藤山寛美さんの戦後の初舞台がウチだったと聞いています」実は、伊勢の古市は島原・吉原に並ぶ三大遊郭のひとつであり、伊勢神宮を参拝する人々をもてなしていた。その近隣に自然と芝居小屋が建ち並び、江戸時代には古市歌舞伎もあったという。「芸の始めは古市…と言われたほど。古市で当たれば上方でも江戸に持って行っても大丈夫だったそうです」元々、関西方面から伊勢へ御参りする初瀬街道沿いにあった旅館の息子だった庄太郎氏。芝居好きが高じて、常宿にしていた旅役者に付いて、とうとう伊勢まで来てしまったという。 |
しかし再開したのもつかの間…戦後の娯楽は芝居から映画へと移り変わっていた。昭和28年に『進富座』は客席数500席を有する東映の専門館『進富映画劇場』として新たなスタートを切る。「全国で映画館が増えた時代ですからね。映画館に変わる時って結構苦労したみたいです。芝居にお客さんが入らなくなり、映画と違って、役者さんが落ち目になってくる様子が見えるわけですからね。売り上げが落ちると役者さんが宿泊する旅館の格も変わってくるわけですよ。だんだんランクが下がって来る役者さんを見るのが母は辛かったようです」GHQの規制が解除され時代劇も作られるようになると、ますます東映が勢いを増し、芝居の舞台は映画スターの舞台挨拶の場となった。「当時は市川右太衛門さんや片岡千恵蔵さんが全盛の頃です。毎年、千恵蔵さんが舞台挨拶に見えられたり、僕は記憶に無いんですけど歌右衛門さんに抱っこされた写真もあるんですよ」昭和29年に“新諸国物語 紅孔雀”が公開されると、200メートル先の大通りまで列が延びて、一日に4500人という動員記録を打ち出したそうだ。「あれが最高の動員記録じゃないですか?行列を見た人が、今日は何ごとや!って大騒ぎになったそうです(笑)」 |
昭和9年には浪曲や漫才なども行い、賑わいを見せていたが、やがて日本は戦争に突入する。出し物に対する国の規制も厳しくなり、しばらくは規制の比較的緩かった京都で興行を続けた。戦後、伊勢大空襲によって焼失した劇場を周辺住民の協力で、物資をかき集めて昭和23年に仮小屋を完成。いよいよ通し狂言“仮名手本忠臣蔵”にて興行を再開する。昭和25年には新生『進富座』として、こけら落しに松竹関西大歌舞伎と銘打って“寿三番叟”他四品目が上演された。(劇場ロビーには当時の番付が飾られている)威風堂々とした風格のある外観の大劇場として甦った『進富座』には、こんな面白い逸話も残されている。芝居小屋だから楽屋や物置など幾つもの部屋が入り組んでおり、誰も入った事がない部屋がたくさんあったという。「祖母から聞いた話しなのですが…どうやらそこに住みついた人間がいたらしいのです。その姿をハッキリと見た者はいないのですが、夜中に売店からお菓子が取られていたので誰かがいるのは間違いない。でも、悪さをするわけではないから、そっとしておいてあげなさい…と、祖母は家族には詮索しないよう言ってましたよ(笑)」何ともほのぼのとした不思議な話である。
|
昭和51年には館名を『伊勢東映劇場』に改め、昭和55年には現在の建物に建て替えた。そして昭和57年には成人映画館『伊勢ロマン劇場(翌年にシネマ・スクエア・レックに改名)』を増設。その2年後には昌光氏が映画館を手伝うようになった。「ちょうど角川映画が出始めた時期で、“セーラー服と機関銃”が大当たりした頃です。場内にお客さんを入れ過ぎて、まだ新しい壁がヘコみましたからね(笑)。立ち見OKの時代ですから、とにかくすごい数字をたたき出しました」別館の運営を任された昌光氏は、成人映画をやめて角川映画と洋画に注力する。初めて上映した洋画の“愛と哀しみのボレロ”が当たったのを契機に東宝東和や日本ヘラルド、コロンビア映画などの作品も扱うようになった。中でも“ゴーストバスターズ”は驚異的な大ヒットを記録。入場するお客様のスピードにモギリが追いつけない状態だった。そして、現在の『進富座』のベースを作った“ニュー・シネマ・パラダイス”を上映する。「試写で初めて観た時に、どうしてもこれをやりたい!って、当時の日本ヘラルドの支社長さんに僕の思いを述べて上映出来たんです」今までに見られなかったお客様の反応も印象的だった。「感動のあまりロビーで泣き崩れる人とか、毎日来て僕たちと一緒に他のお客さんに礼を言ってくれる人とか…色々な事を見せてくれた映画です」しばらくは順調だったが、近隣にシネコンの建設計画が持ち上がると同時に、少しずつ客足も遠のき、昌光氏は映画館から距離を置く。平成9年に別の興行会社に運営を委ねるも5年後にはその会社も手を引いてしまった。その時、映画館を手放す話しが出て来たが、昌光氏はそれに猛反対。再び映画館に戻る事を決めた。館名も旧屋号の『進富座』に戻して、本格的なミニシアターとして平成14年に再スタートを切る。4年後には別館も再開させた。 それから15年が経ち、作品が替わるたび足しげく通ってくれる常連さんも増えた。「上手く行かなくて落ち込んだり迷ったりする時に助けてくれるのが映画だった」という昌光氏は、どんなに忙しくても上映作品は必ず自分の目で観て決めている。「こんな映画があったの?って驚いてもらえる作品を探し出すのが僕の使命ですから」コチラで上映する作品は年間で約90本ほどだが、その倍以上は観ているという。「言い換えれば、その分だけ断っているという事だよね。断るのは本当に難しい…せっかく紹介してくれた配給会社の人に上手く断れたら大したもんだよ」と苦笑する。選定の基準は出来るだけ偏らずに、料理でいえば和食だったりフレンチだったり…とにかくごった煮になるように心がけているという。「例えば、“岸辺のふたり”という短編のアニメのようなすごい作品が突然ポッと出て来るから手を抜けないんです」その一方で、偏り過ぎて「私の映画館」にならないように気をつけていると語る。ミニシアター系をやるようになって、以前より興収は減ってしまったが、逆に良い作品に出会う確率は高くなったそうだ。「その分、経営的な悩みも増えましたが(笑)そんな時に気持ちを和らげてくれるのは、良い映画をやっているんだという思いなんです。やめようと考えた事は何度もあったけど、結局、映画とお客さんが助けてくれるんですよね」 |
  |
    |
「勿論、お客さんが求めている映画をやりたいけど、ウチみたいな映画館は、何でもかんでもお客さんが入る映画ばかりやればイイという事ではない」例えば今年のヒット作“この世界の片隅に”をロングランで続ける事に昌光氏は待ったを掛けた。「そこには葛藤があったんです。続けていればまだまだ入ったと思うのですが、そこに流されてしまうと大事なものを失ってしまう…と思ったんですよ。続ける事で出来ない作品が出てくる、だから予定通り切りました」また、こうしたメディアの影響で話題になった作品を掛けると、いつもは来ないお客さんが来て、全く違う映画環境になってしまう事を昌光氏は恐れる。「今まで常連のお客さんと一緒に築いてきたものが、台風のようにワーっと荒らされて、その後は何も残らない。“この世界の片隅に”は良い映画だけど、それじゃ、ずっと僕が良いと思って上映してきた映画は何だったんだろう…と思うんですよ」確かに、近年のヒット作が生まれる傾向として、SNSを更にメディアが拡散する事によって今までに見られなかった人の流れが出て来た。それをキッカケに映画館に来てくれる人が増えるという事も大切だが、誤解を恐れずに言えば、一方で映画を観る側の意識が段々幼稚化しているのも事実だ。マナーもそうだが、例えば吹き替えじゃないと観ないという若者が増えているのもそのひとつ。「そういった状況の中で、ウチでやっている映画は、ある程度イマジネーションを使わないと入って来ないものばかり。そこに関しては厳しく守って行きたいと考えています。だから、若い人たちには背伸びするつもりで観に来て欲しい」 ここに一冊の本がある。昌光氏の三女・結さんが卒業制作で書かれた本だ。その中には4世代に渡って『進富座』と向き合った家族の歴史が綴られている。映画を観る行為が多様化している現代において、コチラのような場所が必要なのだ…と改めて思う。「プロというのは、絶対に変えてはいけないものと、変えなくてはいけないものの違いが分かる人」という昌光氏の言葉がよく理解出来る。大切なものはデジタル化する事では決して無いのだ。ひとつひとつの映画に対する思い…そこで映画館と観客の気持ちが重なれば、その映画は間違いなく名作となるはずだ。(取材:2017年4月) |
【座席】 『本館』120席/『別館』47席 【音響】SR 【住所】三重県伊勢市曽祢2-8-27 【電話】0596-28-2875
|