     |
町の並木に潮風吹けば 花散る夜を惜しむよに 伊勢佐木あたりに灯りがともる…横浜市関内駅から黄金町方面に長く延びる商店街・伊勢佐木町界隈を青江三奈が歌った昭和の名曲「伊勢佐木町ブルース」だ。メイン通りの伊勢佐木モールは関東屈指の商店街であり常に多くの人々が行き交っている。平行する路地には数多くの飲食店が軒を連ね、夕方あたりからポツポツと店の灯りが通りを照らす。まさに、その情景が歌われた路地に町の映画館『横浜シネマリン』がある。昭和30年7月8日、吉本興行が運営する“横浜花月劇場”という館名で、40円均一の大映専門館としてオープンするも8年後に吉本が撤退。古くから続くとんかつ屋の“かつ半”が経営を引き継ぎ、昭和39年に“イセザキシネマ座”という館名で松竹チェーンとして再オープン。運営に関しては映画館の経験が無いため、近隣にあった“横浜ピカデリー”の支配人が兼務していた。日本映画の斜陽期と呼ばれていた時代には日活ロマンポルノの上映で危機を凌いで、大手シネコンが近隣に進出してきた近年まで、何とか手堅く生き残ってきた『横浜シネマリン』だったが、フィルムからデジタルへと移行する平成26年3月、60年の歴史に幕を下ろす…という道を選んだ。それから間もない12月13日、ミニシアターに生まれ変わり、横浜の根強い映画ファンの前に再びその姿を表した。 |
| 「私の地元・横浜で観たい映画を上映出来る映画館を残したかった」と語るのは茅ヶ崎と横浜の映画サークルで活動をされてきた支配人の八幡温子さんだ。長年住んでいた茅ヶ崎に映画館が無かった時代、有志と共に上映活動をされてきた八幡さんが、横浜に戻ってくると、老舗と呼ばれていた名物シアターが次々と閉館、10館以上も軒を連ねていた映画館も数館を残すのみとなっていた。映画サークルの仲間と、いつかは自分たちで映画館を持ちたい…という夢を持ちながら活動を続けていた八幡さんの元に、『横浜シネマリン』が閉館するという情報が持ちかけられたのは、ちょうどそんな時だった。「即答しなくてはいけなかったので、とにかくやります!…と先に返事だけして、後はどうにかなるかなと(笑)。このチャンスを逃したら、もう映画館を持つのは無理だと思って、私一人でもやることに決めました」そして、その思いに賛同してくれた第一線で活躍する映画館のプロ集団が集まってくれた。映像・音響設計をアテネ・フランセ文化センター制作室の堀三郎氏、内装・照明デザインを岩崎敬氏、そして番組編成には元・吉祥寺バウスシアターの西村協氏が協力体制を組み、復活プロジェクトがスタートする。そして老朽化した既存の映写機から、“渋谷オーディトリウム”で使われていた35ミリ映写機を譲り受け、更にユーロスペースの支配人・北條誠人氏の口利きで、フィルムを扱える映写技師を紹介してもらいフィルムとデジタルの上映を可能にした。 |
しかし、ここから想定外の難題が次々と八幡さんの前に立ちはだかる。「まぁ何とかなる…という気持ちで改装を始めたところ、60年前のまま騙し騙し使っていた感じで根本から手を加えなくてはならない箇所がいくつもあったんです」例えば、配電盤が旧式のタイプでヒューズが丸出しだったり、壁も雨が降るたび水が染み出てくるなど、外見だけでは分からなかった事が日に日に明らかになってきた。「決定的だったのは、空調機を全く回していなかったらしく、一度オーバーホールのため夜中に動かしたのですが…そこで機械の中に繁殖していたカビ菌をばらまいてしまい、映画館全体にカビが生えちゃったんですよ」その時の光景は今でも忘れないと語る八幡さん。場内の座席がカビで白く覆われてしまい空調機を新しく買い替えなくてはならない局面に迫られる。 「そこで初めて、周りの人からココは諦めた方がいいよと言われたんです」内装を担当した岩崎氏は、残っていた設計図が尺で書いてあった青焼きの図面だった事に驚き、工期の半分は発見する日々だったと語っていた。また、設備を担当した堀氏は、これまで手がけた20館近くのミニシアターの中でも想像を超える大変さがあったと振り返る。「こんなところで諦められない」という八幡さんの熱意もあって、電機のコンサルタントが安い空調機を探し出してくれたおかげで再開の道が開けたものの、予定外の出費と工事にスケジュールは大幅に遅れ、12月12日のプレオープン当日もギリギリまでロビーの床を張る作業が続いていた。ちゃんとしたシミュレーションもままならない中で、不慣れな受付対応を助けてくれたのは、ユーロスペースからの応援だった。「受付に何が必要かのノウハウも教えていただいた上に、一緒に買い出しも付き合ってくれたんですよ。本当に助かりました」と当時を振り返る。オープンから更に3ヵ月、間に合わなかった内装も営業を続けながら閉館後に少しずつ手を加えて、今年の4月にひとまず工事は終了を迎えた。 |
     |
前もって整理券付きの入場券を購入して、予告編が流れるモニターを横目に、劇場に隣接する昭和の雰囲気を残す喫茶店“あづま”で、ケチャップをタップリ使ったナポリタンを食べてギリギリまで過ごす。休館している間は、お客さんが減ってしまった…とお店の方が言われるほど、訪れる映画ファンには定番のコースだ。劇場のロビーは、中央に映写室と事務所を構えたコの字型で、格子のアクセントを付けた鏡の壁面と木のベンチが目に優しく、待ち時間も落ち着ける空間となっている。かつてウナギの寝床と呼ばれた縦長の場内は、165席の前4列を撤去し102席に変更。更に、スクリーンを手前に設置してデジタル映像のコントラストが理想的に再現出来るよう調整した。また、天井を這っていた空調ダクトも取り払われた分、スクリーンも大きくなり、壁に張り巡らしたグラスウールが音の反響を抑えて理想的なサウンドを実現している。「初めてのお客様から、観やすくて音響も良いから満足しました…という声をいただいているんですよ」と言われる通り、着実にリピーターが増え始めている。 プレオープンでは、小津安二郎監督のサイレント“青春の夢いまいづこ”をサイレント映画ピアニストの柳下美恵さんの伴奏付きで上映。サイレント時代の作品を現在の映写速度で再生するとコマ数の違いから不自然な動きになってしまうところを映写機技術者の加藤元治氏によって速度を細かく調整、当時の動きを再現してくれた。「デジタルの時代だからこそ、フィルムの原点に返った作品を紹介して行きたい。優れた作品がたくさんあるのに、そのままオクラにしてしまうのは勿体ない…新しい作品と合わせて紹介する事で、若い人たちに、こんな映画があったんだと発見してもらえたら良いですね」また、松井久子監督のドキュメンタリー映画“何を怖れる〜フェミニズムを生きた女たち”を上映するため、映画館での公開を考えていなかった松井監督に直談判。「社会で自立して生きている女性を取り上げた作品を積極的に紹介したいと思っていたので、愛知国際女性映画祭で観た時、どうしてもウチで掛けたいと思ったんです」当初は難色を示していた監督もそんな八幡さんの熱意に上映を快諾してくれて、多くの女性客が来場した。また5月にはドキュメンタリーカメラマン大津幸四郎の追悼上映として、1ヵ月ぶっ通しで10作品の上映を敢行。「周りから無茶だと言われましたが、こんな時代によくこのような映画を撮ったな…っていう生身の人間の凄さを観客の皆さんに読み取ってもらいたかったんです」 |
  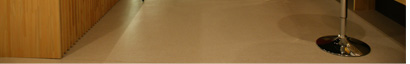 |
「慣れない映画館の一日を回すのが精一杯で、闇雲に毎日を過ごすだけだった」オープンから半年が過ぎて八幡さんが思うのは「今から思うと、なんであんなに大変だったんだろう?何より映画が好きなのに映画を観に行く暇がないのが辛かった」という事。「意外だったのは長年やってきた映画館だから、誰もが知っていると思ったのですが…最初は館名を言っても分からないという方が多かったのに驚きました」今まではメジャー系の作品が中心だっただけに、ミニシアターの客層とは全く異なるというのが大きな原因かも知れない。「だから当面の目標は多くの人を巻き込む事かな…と思っています」そこで八幡さんは映画館を若いクリエイターと、お客様が交流出来るサロンのような場所にしたいと考えているという。最近では自主映画を持ち込んでくる熱意のある若者たちにも門戸を広げている。「おかげで、色々な団体から一緒に何かをやりませんか?というお話をいただいているんですよ。とにかく何でもOK!協力しますよ!という姿勢で(笑)基本は映画を上映する…というスタンスは崩さずに、何でもチャレンジしたいと思っています」(取材:2015年4月) |
  |
| 【座席】 102席 【音響】 SRD・デジタル5.1ch
【住所】神奈川県横浜市中区長者町6-95 【電話】045-341-3180
|
