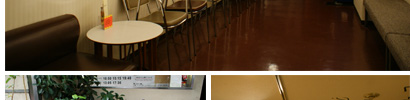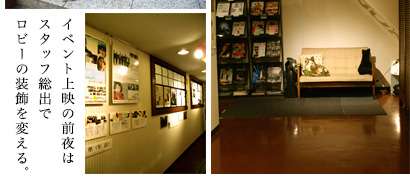|
JR山手線の目黒駅西口を降りてすぐ…心憎い二本立てでファンを魅了してやまない名画座がある。常に全力で上映可能な作品を探し出し、スタッフ総出で観客を出迎えてくれる『目黒シネマ』だ。昭和30年…当時、次々とヒット作を送り続けた大蔵貢社長が率いる大蔵映画(株)が経営するチェーン館として、660席を有する『目黒ライオン座』と、地下に290席を有する『目黒金龍座』の2館体制でオープン。間もなく『目黒ライオン座』は成人映画館、『目黒金龍座』は洋画を中心とした名画座となり、現在の建物になった昭和50年に地下の劇場のみを残して『目黒オークラ劇場』という館名で再オープンする。現在の館名となったのは、その翌年の昭和51年のことだ。かつてキネマ旬報の名物コーナーだった「われらの映画館」に寄稿されていた故・伊藤勝男氏は“都内のどの劇場よりも名画座らしい泣かせる劇場”と賛辞を贈っていた。当時のラインアップを見ても、名画座とは名ばかりのムーヴオーバー館が多かった時代において、コチラが抜きん出た存在だった事がうかがえる。 |
それから40年以上が経った現在…『目黒シネマ』のラインナップを見ると『目黒金龍座』イズムがしっかりと継承されているのが判る。「前の支配人から運営を引き継いだ時に、ずっと守って来たものを僕の代では絶対に潰さない!と誓ったんです」と語ってくれたのは支配人の宮久保伸夫氏。かつて観客として訪れていた宮久保氏もまた、目黒の主と呼ばれていた前支配人がチョイスされていた番組に惹かれていた一人だった。「ウチのお客様は僕以上に目が肥えていらっしゃいますので、生半可な事をやると、これはどういう意味で組み合わせた2本ですか?とご指摘を受けるので気を抜けないですよ」と笑う。こうして考えると名画座というのは振り幅の広さでは、シネコンや封切り館には無い豊かさがある。その豊富な作品群の中から新作と旧作を組み合わせたり…最近ではフィルム時代の作品とデジタル以降の作品を組み合わせたりとか…こうした比較や遊びが出来るのも名画座の醍醐味と言えるだろう。 「名画座の良いところは、なかなか袂が合わせられないところを接着剤みたいに繋げてしまえる妙味ですかね。古い例えですが、全日本プロレスと新日本プロレスを一緒にやれちゃう…みたいな(笑)」そういった意味で先日上映された“バットマンVSスーパーマン”と“シビルウォー”なんて、正に夢の組み合わせではないか。「二本立ては一作品だけを宣伝して売るものではない。更にそこからプラスアルファみたいな売り方があって、そこには劇場側のセンスも出てしまうので、それが面白いですよね。ひとつひとつの作品は、勿論どれもが素晴らしいのですが、それを組み合わせる事によって、更に世界観が広がると思うんです」だからこそ、敢えて組み合わせの意味を提示しない時もあるという。それは謳わない事によってお客様の方で色々と考える楽しみを残したいから。「例えば監督とか作家さんに、何でもかんでも、このテーマは何ですか?って聞くのも野暮じゃないですか。それは観た人が感じたものが答えだと思うので…」 |
ここ数年の『目黒シネマ』は、ひと味違ったプログラムを提供している。通常の二本立てに加えて、<自作と観る監督チョイス>と<俳優チョイス>そして<名作チョイス>という企画上映を行っているのだ。「<自作と観る監督チョイス>は、何と組み合わせて欲しいですか?って、監督本人に併映作品を決めてもらっちゃう企画なんです」最近では宮藤官九郎監督の“TOO YOUNG TO DIE ! 若くして死ぬ”で宮藤監督は石井輝男監督版の“地獄(1990)”をチョイスした。「今回で第5弾になるんですけど…すごいでしょう?クドカンさんに選んでもらうなんて。中には権利が切れていたりフィルムが無いものもあるので、まずは3つ選んでもらうんです。“地獄(1990)”は、ウチの会社がOP映画だった頃、成人映画として配給したんです。ただ石井監督がお亡くなりになってから連絡先が分からず色々と調べましたんです。そうしたら数年前に京都の映画館でやっていたので、電話をかけて連絡先を突き止めることが出来て…実現出来ました」という宮久保氏の言葉からもお分かりの通り、コチラの仕事は我々の目に見えない水面下で行われているのだ。
|
「皆さんレアなものを上げられるので、まずフィルムを探すところから始まるんですよ。フィルムが見つかったとしても、古い作品ですから上映出来る状態じゃないものもあったりして…その時は、監督にお伝えして、次の候補を選んでもらう。結構、時間と手間がかかるのですが、宝探しみたいで楽しんでますよ」ちなみに第一回目は、是枝裕和監督が“海街diary”の併映に選んだ長谷川一夫の“鶴橋鶴次郎”だった。その理由もただ単純に、観たいから…という事。「そんな理由でも良いんです。だって監督が観たい映画を選んでもらうコンセプトさんですから(笑)」何でもありだからファンも気軽に楽しめるのだ。その後、大根仁監督は“バクマン”に対して漫画家つながりの“トキワ荘の青春”。山田洋次監督も“母と暮らせば”の併映に成瀬巳喜男監督の“お母さん”を選び、塚本晋也監督は“野火”に市川崑監督バージョンの“野火”を選ばれている。同じく今年から仲間入りした<俳優チョイス>では、竹中直人監督作品常連の田中要二氏が自身が俳優としてのターニングポイントとなった2作品をトークショーも交えて上映されている。 |
そして、既に『目黒シネマ』の名物として浸透しているのが<名作チョイス>。おかっぱLOVEと銘打って、“地下鉄のザジ”と“アメリ”を組み合わせたり、最近では、“ピンポン”と“鉄コン筋クリート”を松本大洋特集としてフィルム上映を行ったところ、多くの観客を動員している。また、監督を招いて開催されるトークショーには回を重ねるごとに、さながら小さな映画祭といった体を形成してきた。キッカケとなったのは、“さよならcolore”の上映が決まった日の事。上映期間中のどこかでイベントをやらせてもらっても良いでしょうか?…と竹中直人監督から直々の連絡が来たのだ。「突然、これから伺って良いですかって…ビックリですよ。当時はリニューアル前で、イベントなんかやった事もなかったですから」そして…竹中監督はトークに加え、アカペラで主題歌を披露してくれて素晴らしいイベントになった。今年の3月にも開催された特集では竹中監督の長編全作品を上映。会期中は、竹中監督が吹き込んだ館内放送が流された。“119”上映時には、主要キャストが全員顔を揃え、来場出来ない赤井英和氏のご自宅にお祝いムービーを撮りに行き、海外にいた浅野忠信氏はマネージャーが撮影したビデオメッセージを送ってもらい、イベントで上映された。他にも岩井俊二監督特集を一ヶ月間ぶっ通しで開催されたり、今や恒例イベントとなった犬童一心監督が主催する市川準監督特集も今年で3回目を迎えている。 この数年で、多くの映画人が『目黒シネマ』を訪れているが、その中で変わり種は、今年の夏にポール・トーマス・アンダーソン監督の音楽ドキュメンタリー“JUNUN”を上映した時のことだ。何と!世界的に有名なロックバンド、レディオヘッドのギタリストであるジョニー・グリーンウッドが来場されたのだ。実はこの作品…海外の映画祭で何回か上映された程度で、それまでは日本未公開。クオリティーの高さに感動した日本のファンが、是非スクリーンで上映すべきだと、直接、アンダーソン監督とメンバーに交渉して実現したものだった。「国内で上映出来る映画館を探して、ウチに辿り着いたそうです。だったら、やりましょう!と、協力させていただきました」しかし、そこからの対応が大変だった。映画館で掛けるとなると、映倫やJASRACに提出して、更に日本語字幕を付けるなど、言わば配給の仕事をやることになったのだ。「字幕が出来上がったのが上映の二日前。そこまで苦労しても上映は一週間だけと決まっていたのですが、その時にサマーソニックで来日していたジョニーが突然、姿を現したのですから、偶然その日に来ていた人は大変ですよ。勿論、ジョニーが来るのは極秘でしたからね」 地下を深く降りてゆくと、通りの喧噪が少しずつ遠ざかっていく。自動券売機で当日券を購入して少し余裕を持ってロビーで待つ。お客様から寄贈された映画関連書籍をペラペラめくったり(何と貸し出しもしてくれる)、特集上映時にはスタッフが全員で知恵を出し合って徹夜で設置した展示物やポスターを眺めたりしていると、時間はあっという間に過ぎてしまう。“バクマン”上映時には壁中にジャンプの漫画で埋め尽くす演出をした。監督特集では本人が描いた直筆の原稿や絵画を飾ったり、売店では作品に合わせたお菓子を近所のお菓子屋に作ってもらい販売したり…と、あの手この手で来場者を楽しませてくれる。 |
やがて、チリ〜ン…チリーン…と、耳に心地よいベルの音がロビーに響く。『目黒シネマ』では上映開始の合図をブザーではなくベルで知らせてくれるのだ。楽しいのはロビーだけではない。週末限定でスタッフ全員が作品のイメージに合わせたコスプレで観客を出迎えてくれる。“キックアス”や“マッドマックス”は御手の物…極めつけは、おかっぱLOVE特集ではオカッパ頭になったりと、やるからには徹底している。「裏を返せば、そういう工夫をしなければ、映画館として生き残るのは難しいと思うんです。普通に映画を観せても、そこに個性がないとつまらない。だからもっと色んな事をやってみたいですね」またコスプレをするにしても映画の邪魔をしてはいけない…と、ネタバレになるような時は、入場時は普通の格好、上映中にメイクをして、終了時にコスプレで見送るという気配りには頭が下がる。 客層は幅広く、珍しいのは20〜30代の女性が多いところだ。名画座というと中高年男性とシニア層というイメージがあったが、しっかりと劇場のコンセプトが固まったリニューアル以後から客層に変化が現れた気がする。「私たちの創意工夫が伝わってきたのかな…と思います。電車を乗り継いで来たお客様に、その時間は無駄だった…と、思って欲しくないんです。来て良かった!と、気持ちよく帰ってもらうために、何をすれば良いのか…を常に考えてます」上映が始まると劇場スタッフは早々に次の仕事に取りかかる。展示物やチラシを僅かの時間を利用してせっせと作っている。そこから更に配給会社などの確認が入り、それが1週間単位で発生するのだ。また、現在はフィルムとデジタルを併用しているため、時間を掛けて編集したフィルムもチェックでやり直し…なんて事はざらという。「だから新しいスタッフには、ウチで働くと映画館の全てが分かるよって言っているんです(笑)大変だけど、楽しいですよね。面白い事をやれば、こんな小さな映画館だってお客様が来てくださるのですから」わずか100席の名画座は、常に可能性を大切にしていて、何にでも挑戦してみる。「これくらいの箱で出来る事を、背伸びしながらやっていきます」と、いう宮久保氏の言葉に、次に何をやってくれるのか?と、考えただけで胸が高鳴ってしまう。(取材:2016年9月) |
|
  |
   |
今回で3回目の犬童一心監督が企画する市川準監督特集イベント。4作品を上映して、11月19日と22日には当時の関係者を招いて、かなり突っ込んだ思い出話しを披露するトークイベントが開催された。スタッフ総出で飾り付けされたロビーは、まさに市川準ワールド一色に染まる。壁には直筆で書かれた原稿用紙や、当時の台本が展示された。あまりに充実した内容のため休憩時間内では足りないくらい。私が参加させていただいた22日には、上映作品“竜馬の妻とその夫と愛人”にちなんで、関わられた製作の富山省吾氏、助監督の井上文雄氏が登壇。中盤には会場にいた照明を担当されていた中須岳士氏も客席から参加(だからやけに照明に時間が掛かる…という批判?的な話題が多かったのか)されて会場は大いに盛り上がりを見せた。好評のコチラのイベントは映画を愛する映画人たちと、映画の送り手である『目黒シネマ』と、そして市川準監督を愛してやまない観客の熱意が生み出した素晴らしいイベントだった。 |
【座席】 100席 【音響】DS・SR 【住所】東京都品川区上大崎2-24-15 【電話】03-3491-2557
|